
| ・記帳代行料金表 |
| ・退職後の手続き |
| ・給与計算代行料金表 |
| ・扶養控除 |
| ・生命保険料控除 |
| ・地震保険料控除 |
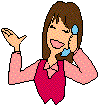 |
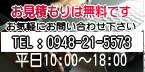 |
 弊社は弥生会計を使用いたしております。 |
サラリーマン時代には、面倒な所得税や住民税も会社が計算してくれ給与から天引き納付までしてくれていました。健康保険、厚生年金にいたっては保険料の半額を会社が負担し、扶養されていた奥様の国民年金も3号被保険者として加入している状態だったのです。
やめてからわかる今まで知らなかったことがたくさんあります。
まず退職すると一番に考えなければならないのが健康保険、国民年金、所得税や住民税、雇用保険(失業保険)等の問題です。
当然雇用保険と労災保険が無くなります。
開業・起業準備にかまけて、何も考えずその場しのぎでやってしまうと後悔しますのでよくよく熟慮するべきです。
①国民健康保険に加入
※市町村単位の運営ですから保険料の計算方法は、自治体によってまちまちですが飯塚市の場合下記のようになっています。全国で一番安い市町村と一番高い市町村では、3倍程度違うと言うことです。傾向として高齢化が進む過疎地ほど保険料が高いと言われています。
1.所得割 (前年度の国保加入の家族全員の所得を基に算出します。) 2.均等割 (一人当たりいくらと決まっています。) 3.平等割 (1世帯にいくらと決まっています。独身でも大家族でも同じ金額です。) 4.資産割 (固定資産課税額を基に算出されます。)
国民健康保険は、もともと自営業者や年金生活者(平均してサラリーマンよりも低所得者)が加入するものですから、退職サラリーマンが加入しようとすると保険料は割高になる傾向にあります。
②任意継続の手続きをとる
※サラリーマン時代に政管健保(社会保険)に継続して2か月以上の被保険者期間がある場合に退職時の健康保険料の倍額を保険料として支払うことで加入できます。扶養家族は、サラリーマン時代と同様に追加保険料無しに加入できます。
通常は、国民健康保険料より割安のことが多いようです。
但し、任意継続ができる期間は2年間です。
③3親等以内の親族の健康保険の扶養となる
※例えば配偶者である奥様が会社員だとすると奥様の扶養家族になることができます。国民健康保険は、前年度の所得を保険料算定の基礎としますが社会保険の扶養判定の基礎は、今後の収入見積もりで判断します。
と言うことは、退職サラリーマンは無職ですから収入は0円です。無条件で扶養になります。
但し、税法では雇用保険(失業保険)は、課税所得とはなりませんが社会保険では扶養判断の収入になります。
通常社会保険の扶養異動届は、奥様の会社の社会保険担当者が提出します。
子供さんがいらっしゃる場合は、問題なく奥様の社会保険の扶養になれます。
以前は、奥様の社会保険の扶養にご主人を入れるため社会保険事務所扶養の異動届を出すと必ず確認の電話がかかってきました。"失業保険は受給しないのか"と失業保険のおよその金額を聞くと所得オーバーですから扶養にはなれませんと言ってきました。並みの事務員さんなら"そうですか?"で終りです。扶養にはなれません。
できる事務員さんは、"雇用保険は、申請から認定、待機期間を経て受給できるまで自己都合の場合では、通常4ヶ月ほどかかります。その期間は紛れも無く無収入ですからその期間は、扶養になれるますよね。"と切り返すのです。結果として扶養になれました。
※①~③については、自己負担額は、現在会社員(政管健保)及びその扶養者も個人事業主(国民健康保険)も同率の3割負担ですから、その点については変わりません。
④保険には加入しない
最後の選択肢は、"病気やけがは気力で治す"という方以外お勧めできません。
"病気になったら国民健康保険に入ればいいや"という勝手のいいことも通用しません。
原則、前の健康保険を喪失した次の月からの保険料を遡って支払わなければなりません。
以上のように選択肢はあるもののどれがベストなのかは、個々のケースによって結果が違ってきますので退職を決意したらまず退職する前に調査されることをお勧めします。
聞かなければ役所は教えてくれません。
退職されると国民年金の加入義務が生じます。国民皆年金制度により強制加入保険です。
国民健康保険料は、自治体によってまちまちですが国民年金は、全国一律です。
保険料は、厚生年金保険料同様毎年あがっていきます。
次のようなパターンがあります。
1.国民年金の1号被保険者として加入する。 2.失業中であることを理由に免除申請をする。(国民年金加入期間としてカウントされます。) 3.健康保険編③の厚生年金・共済組合の配偶者(第2号被保険者)の扶養となり3号被保険者となる。
ベストは、3です。それができなければ、当面は2の免除申請をすることで様子見がベターでしょう。
起業・開業するまでは、無収入なのですから堂々と免除申請をしましょう。
個人住民税は退職した月によって違いますが、退職するとたいていの場合2~3ヶ月後に住民税の納付書が送付されてきます。前払いの源泉所得税に対して、個人住民税は、前年度の所得に対する後払いの確定課税ですから退職して無収入になっても納付しなければなりません。
ちなみに市町村関連は、前年度の所得を算定基礎としていますので児童扶養手当の現況届けなども自営業者扱いになり所得制限でカットになる可能性は高くなります。
所得税は
サラリーマン時代は、源泉所得税として給料からの天引きで納付していましたから、退職後に所得があれば確定申告をして納付することになります。退職した年は、通常年末調整をしていませんので確定申告をすれば税金が戻ってくる場合が多いです。
ちなみに失業保険は、所得としてみなされませんので課税されません。
雇用保険の保険給付には色々ありますが、事業を始めようとする方に直接関係してくるのは「基本手当」と「再就職手当」の2つでしょう。
①基本手当
基本手当の受給要件
基本手当は、雇用保険の被保険者が離職して、就職の意思および能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態にある場合で、離職の日以前1年間(1年間に疾病、負傷等の期間があった場合には、最長4年間。また、当該1年間に短時間労働被保険者であった期間があった場合には、その期間に1年を加えた期間)に賃金支払基礎日数が14日以上の月が6ヶ月以上であったときに基本手当が支給されます。
平成19年10月1日以降に一般労働者と短時間労働者の被保険者区分が廃止され、基本手当の受給資格要件が一本化されています。
平成19年10月1日以降に離職された方の基本手当受給要件は、次の通りです。
| 特定受給資格者 (倒産・解雇等により離職された方) |
過去1年間に被保険者期間 (賃金支払基礎日数が各月11日以上) 6ヶ月以上あること |
| 一般離職者 | 過去2年間に被保険者 (賃金支払基礎日数が各月11日以上) 12ヶ月以上あること |
同一の事業主の適用事業に引続き雇用された期間に被保険者区分の変更があった場合には、その区分の変更があった日の前日に離職したものとみなすこととされています。これを「みなし離職」といいます。
◇受給資格の決定
受給資格とは、公共職業安定所長が基本手当を受給できる資格がある者と認定することをいいます。
受給資格者であると認定される3つの要件
1.離職により被保険者でなくなったことの確認を受けたこと
2.労働の意思および能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること
3.算定対象期間(離職の日以前2年間)に被保険者期間(賃金支払基礎日数が各月11日以上ある月)が通算して12ヶ月以上あること
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、通算して6ヶ月以上あること
基本手当を受けるためには、上記の受給要件を満たしているほかに、その人が公共職業安定所に出向き、求職の申込みをしたうえで、失業の認定をうけなければ
なりません。
◇基本手当受給の手続き
住所を管轄するハローワークに、ご本人が直接下記の書類を持参して手続きして手続きしてください。| 1. | 離職票-1 | これらの書類を持参して住所を管轄するハローワークに提出し、まずは職業相談窓口で「求職票」を作成します。 求職票には、これまでに経験した仕事内容や退職理由、希望する仕事、月収などを記入して提出します。希望する職種に関して職員のアドバイスを受けた後は、雇用保険給付課の窓口に行き、持参した書類を提出。受給資格の確認を受けたら、初日の手続きは終了です。 受給資格決定日から7日間は「待期期間」といって、受給の対象外になります。 後日説明会があり、そこで説明される受給方法に従って手続きを進めていきます。 |
| 2. | 離職票-2 | |
| 3. | 雇用保険被保険者証 (入社時に交付されています。紛失している場合は、来所の際にお申し出ください。) |
|
| 4. | 最近の写真2枚 (たて3cm、よこ2.5cmで本人と確認できるもの) |
|
| 5. | 運転免許証または住民基本台帳カード(写真付き) これがない場合は、次のうち2種類 (1、2または3から各1種類で合計2種類) 1.パスポート 2.住民票(住民票記載事項証明書)または印鑑証明書 3.国民健康保険被保険者証(健康保険被保険者証) |
◇失業認定の流れ
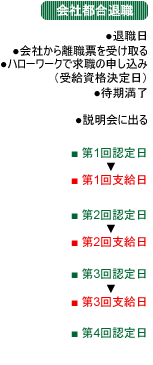 |
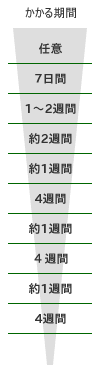 |
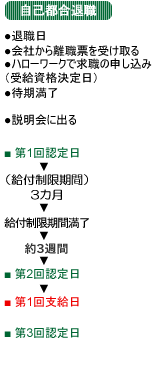 |
待機満了の日の翌日から認定日の前日までの4週間のうち失業の状態にあったと確認された日について支給されます。 認定日に本人が出頭し、失業の認定を受けないと支給されません。 自己都合等により離職した場合は、待機期間満了後3ヶ月間は給付制限期間となり、支給されません。 |
◇基本手当の日額
基本手当の日額は、離職前の賃金を基準として決定されます。
賃金日額=(離職した日の直前6ヶ月間に決まって支払われた賃金の総額)× 1/180
基本手当の日額=賃金日額に所定の率を乗じた額(所定の率は次の表を参照してください)
基本手当の日額
| 離職時年齢 | 賃金日額(W) | 給付率 | 基本手当日額(Y) |
|---|---|---|---|
| 30歳未満 又は 65歳以上 |
2,070円~4,080円 | 80% | 1,688円~3,328円 |
| 4,080円~11,820円 | Y=(-3W×W+74,160W)÷77,400 | 3,328円~6,030円 | |
| 11,820円~14,140円 | 50% | 6,030円~6,495円 | |
| 14,140円~ | Y=6,365 | 6,365円(上限額) | |
| 30~45歳未満 | 2,070円~4,080円 | 80% | 1,688円~3,328円 |
| 4,080円~11,820円 | Y=(-3W×W+74,160W)÷77,400 | 3,328円~6,030円 | |
| 11,820円~14,140円 | 50% | 6,030円~7,215円 | |
| 14,140円~ | Y=7,070 | 7,215円(上限額) | |
| 45~60歳未満 | 2,070円~4,080円 | 80% | 1,688円~3,328円 |
| 4,080円~11,820円 | Y=(-3W×W+74,160W)÷77,400 | 3,328円~6,030円 | |
| 11,820円~15,550円 | 50% | 6,030円~7,935円 | |
| 15,550円~ | Y=7,775 | 7,935円(上限額) | |
| 60~65歳未満 | 2,070円~4,080円 | 80% | 1,688円~3,328円 |
| 4,080円~10,590円 | Y=(-7W×W+132,720W)÷130,200 Y=0.05W+4,236 のいずれか低いほうの額 |
3,328円~4,864円 | |
| 10,590円~15,060円 | 50% | 4,864円~6,916円 | |
| 15,060円~ | Y=6,777 | 6,916円(上限額) | |
| ※ 端数 1円未満切り捨て | |||
◇基本手当の給付日数
基本手当の給付日数(所定給付日数)は、受給資格者の離職の日における年齢、被保険者であった期間等に応じて、次の表のとおりです。
1.一般の離職者
| 被保険者期間 | 1年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
|---|---|---|---|
| 全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
2.障害者等の就職困難者
| 被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 |
|---|---|---|
| 45歳未満 | 150日 | 300日 |
| 45歳以上65歳未満 | 360日 | |
| ※身体障害者、知的障害者、刑余者および社会的事情のより就職が著しく阻害されている人など | ||
| 被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 区 分 | |||||
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
| 30歳以上35歳未満 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 35歳以上45歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | |
| 45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
②再就職手当
安定した職業(事業を開始した場合も可)に就いた受給資格者であって、次の要件すべてに該当する者には再就職手当が支給されます。
1.上記支給残日数があること
2.待期(7日間)が終わっていること
3.3か月の給付制限がある方は、はじめの1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で雇用されたこ
と
4.原則として、雇用保険の被保険者となっていること
5.1年を超えて勤務することが確実であること
(生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあた
って一定の目標達成が条 件付けられている場合、または派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の
更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
6.離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前事業主と密接な関係にある事業主も含む)に雇
用されたものでないこと
7.雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ来られた日より前に雇用が内定していた事業主に雇用されたも
のでないこと
8.再就職の日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
・再就職手当
・早期再就職支援金
・常用就職支度金
・常用就職支度手当
9.就職をした後、すぐに離職したものでないこと
支給額 = 基本手当日額 × 支給残日数 × 3/10
雇用保険を受給しながら開業準備をしようとお考えの方にご注意。
雇用保険の受給資格ひとつに、"就労する意思があること"、"就労する能力があること"つまり"求職活動をしている"ということです。
雇用保険の趣旨としては、当然と言えば当然のことですが自営業や法人の設立準備をしている人は、受給資格の欠格事項に該当します。
20年も30年も雇用保険を掛けてきたのに掛け捨てなのかとあきらめるのは早いですよ。
雇用保険の受給資格のある被保険者が起業するときに受給できる助成金がありますのでそれを活用することをお勧めします。
受給資格者創業支援助成金は最大で起業に要した費用の3分の1上限200万円まで助成してくれます。
それ以外にも
高年齢者等共同就業機会創出助成金、地方再生中小企業創業助成金等の創業助成制度がありますので、該当しそうな助成金を調べておいて損はないと思います。
〒820-0067 福岡県飯塚市川津400-3
藤レジデンス102号
TEL:0948-21-5573
福岡県内の主な営業エリア:福岡市、飯塚市、嘉麻市、桂川町、田川市、田川郡(糸田町、添田町、香春町、川崎町、大任町、赤村、福智町)
北九州市、直方市、宮若市、鞍手郡(鞍手町、小竹町)、糟屋郡(宇美町、粕屋町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町)他